
2000年、21世紀の幕開けの年。巷では漠然とした希望や期待感が蔓延し今年のみが特別な年になるのだという気分に沸いていた。しかし、加藤は42歳になったという現実のみ感じていた。もっと何か特別なことを成し遂げてもいい歳なのではないか。
はじめから音楽を志したわけではない。が19歳でプロ入り。成行きだった。ここでは詳しくは語らない。ジャズ界デビューは猪俣猛トリオ。だが27歳と遅く、それからも鈍牛のような歩みだった。ジャズのルーツを探るべく33歳で単身ニューヨークへ渡り3年間本場の空気を吸った。1992年にはニューヨークでマイク・スターンをゲストにCD(Something Close To Love:キングレコード)を録音。B-HOT CREATIONSというネーミングはこの時につけられた。B-HOTは(熱くなれ)といった意味であえてBe動詞をBと表記することにした。以後B-HOT CREATIONSは加藤の音楽全般を指す。
このころはジャズを生んだアメリカ、何もかもを取り込むその懐の深さにあこがれ、盲目的にジャズに傾倒していた。が、米国に一人、ジャズを目指す日本人が在るという現実に対し、日本人がジャズを演奏する意義というものを考える時期でもあった。
「俺のこれからの音楽」「日本人としての音楽」「自分の音楽を全うしよう。」
そして1994年帰国。
請われた仕事は断らなかった。そして順調に仕事をこなし、ジャズ・べーシストとしてもそれなりの業績を残してきた。
ベース・プレイヤーの成功とはいかに他の楽器演奏家に多く雇われるかということにある。使ってもらわれなければ仕事が発生しない。いわば専門技術職である。べーシストとしての成功を望むならすべての音楽ニーズにこたえる技術を持てばいいのだ。そう考えていた加藤だったが一個人のベース弾きとしてはどうだろう?加藤のベースに好意を持ってくれた人たちは加藤の演奏から何を感じたか、また感じたいか。
加藤はそれを演奏しなくてはいけないのではないだろうか?
そういった考えからソロの活動の必要性を感じ、着手したベース独奏アルバム(Old Diary:サウンドヒルズ1998年)は全世界で発売され、徐々にベースに焦点を当てた演奏を始めた。普段伴奏楽器であるベースをソロ楽器同様前面に押し出して見せたのであるからこの先この活動は多難、簡単ではないとそれなりの心構えはあったが、ソロを始めたことにより同時に自分の演奏に足りないものもはっきりと認識できるようになっていた。
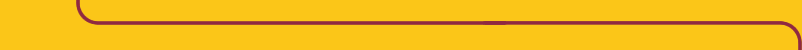
そんなころあのバンドを見たのである。それはベースレスのトリオでヴォーカル、ピアノ、ドラムスの編成。そして加藤のこれからの演奏に足りていないもの、欲しているものをそのバンドのピアニストは弾いていたのである。背が高く痩せてアフリカ人のようなマントのように長い黄色っぽい模様の入った衣装をつけていた。衣装も演奏もユニークである。まだ27歳であった田中信正である。加藤の10歳下である。
加藤の活動は年上のミュージシャンに請われて演奏することがほとんどであった。上の人から学ぶものは山ほどあったし、それなりに学んできたが加藤は若い世代、それも加藤の考えも及ばない新しいサウンドを持っている連中、そいつらと演奏する必要があると感じたのだった。
当時加藤は佐藤允彦と演奏する機会が増えていた。佐藤允彦は同業のピアニストたちが一目置くというより無視できない存在である。そしてそのべーシストはかなり厳しい演奏を強いられていた。ジャンルも広範囲におよびフリージャズまでもがポップな曲と同じウエイトで演奏するテクニックを求められていた。またイレギュラービートや民族音楽に関しても然りである。したがって加藤には必然的にテクニックの向上がみられた。
また田中は偶然にも佐藤允彦に師事していた。佐藤はメーザーハウスの校長。佐藤の語ったところによるとピアノ科の橋本一子から「私の手に負えない」ということで佐藤に相談があったそうだ。佐藤は田中の非凡さを即時に見抜き他のピアノ科の生徒とは隔離し直接の指導をする。そして佐藤のアドバイスにより立ち上がったトリオがその田中が演奏していたトリオ(BOJO:第一回横浜ジャズプロムナード・コンペティションでグランプリ、個人賞ベストプレイヤー賞を獲得)なのである。
これは余談だが、田中と話しているうち彼が好きなピアニストの一人にジュリ・アレンをあげた。くしくも私がNYで録音しようとした人である。当時彼女は妊娠中で共演は実現しなかったが。
また田中は山下洋輔トリオで一世を風靡したドラマー、森山威男に惚れられていた。「信正見参」などとタイトルをつけられたCDがあるくらいだ。ポスト山下的な才能を見出していたのであろう。
田中は実に不思議なというかユニークなピアニストである。まずジャズの伝統を引き継いでいるようでそうでない。ジャズのリズム、グルーブを持っているようでそうでない。ハーモニーに関してはメシアンまでよく研究されている。かといって実に単純な和音を使うのに躊躇しない。ピアノは打楽器であることも良く理解しているのだ。(Take The “A” Trainがいい例である)



2000年ある日、六本木にあったクラブ「BASH」でヴォーカル伴奏の仕事があった。店には少し早い時間にそのリハーサルのため入った。しかしそこにはグレッチのドラムがセットされていた。その日のギグにドラマーは頼んでいない。
「この勘違いの馬鹿野郎は誰だ。」
しばらくして現れた若者は「すみません、すぐ片づけます。昨日ライブだったんです。」
少し話してみると気のいいやつで好感が持てた。その夜は空いているというので、
「いっしょにやるか?」「やらせて下さい。」
そのままのセットを叩いてもらった。よくスイングして粗削りだがいいビートを持っていた。なによりベースとドラム、リズム・セクションとしてのコミュニケートがスムースだった。
父親は高校の音楽教師、母親は絵を描いているそうだ。高校生の時からジャズクラブに出入りし繁華街で演奏していたらしい。不良である。名前と違う。
孤高のべーシスト鈴木勲に引っぱられ広島から出てきたそうである。その時は本田竹廣トリオでも演奏していた。加藤の20歳下であった。
「俺はあと2,3年で世界一のドラマーになります。」
「馬鹿だな、こいつ」と思った。が、ドラマーはこうでなくちゃいけない。本能を感じさせる野生児がいいのだ。ドラミングは瞬間が命である。ひらめきをたたき出すには躊躇するような頭ではいけない。失敗でも間違ってでもいいが竹を割ったような潔さが要る。
加藤は「未だに世界一にはなれていないじゃないか。」と言ってからかうが本人はあっけらかんとしている。こういう神経もドラマー的である。

まずはトリオで
このドラマーを得て田中とのトリオのアイディアが浮かんだ。加藤が自由に弾ける空間をこの若い二人は創ってくるような予感がした。そしてそれは事実だったのである。
演奏にまとまりは無く完成度は低い。しかしそれはどうでもよかった。それに完成度が低くなるのは加藤がいろいろ試すからである。ベースが動き回ると音楽も荒れるものだ。完成を目指すわけではなく自由にやって創り上げていくという行為が加藤の目的だったからだ。加藤は他のバンドで得たアイディア、テクニックを試した。また彼らからは新しい何かを感じ多くのものを学んだ。トリオは発展するわけではないが演奏は楽しかった。オリジナルも多く書いた。トリオは型が無かった。それはやはり田中の影響によるものである。彼のピアノは独自のリズムフィーリングをもっていた。ビバップを弾いてもビバップにはならず、何を弾いても型にはまらない。
加藤はいつかこのトリオで何かできるという漠然とした期待を持っていた。



加藤はトリオをメインに据えた。活動の場は限られたがそんなことははなから承知である。面白がる人はいたがほとんどの聴衆にはそっぽを向かれる。そういった活動の中に嶋津健一(P)との出会いがあった。当時彼は尺八、能、書道、舞踏など異種芸術との融合を模索していた。彼の中で加藤は異色のべーシストと映ったのであろう、しばらく行動を共にした。その彼を中心とするサークルの中に加藤に興味を持つ人物がいた。
嶋津の音楽は独自の味わいを持っていた。しかしそのテイストは万人受けするものではなかった。だがそれをこの人は好む。
青春時代はジャズ喫茶(新宿DUG)、レコード業界、販売も制作もこなしてきて自己のレーベル(ローヴィング・スピリッツ)を立ち上げた人物である。
かなり偏った趣味であることは否めないがサムシング・スペシャルということにはとことんこだわっている。俗な歌ものなどは「つまらん」と言い切る。
加藤は「面白い」と思った。自分が微妙にはみ出していることは分かっている。
はみ出し者を集め、真っ正直に標準的な器にもろうという奇怪な企みがB-HOT CREATIONSである。これを聴かせてみようと考えた。

そんなとき、斉藤が「おもしろいのがいる」ということで紹介されたのがNOBIE。
彼女は我々がよく出演していた「BASH」でたまにバイトをしていた。東京大学薬学科卒の才女である。もちろん加藤はそんなことは知らなかった。「何か若いのがいるな。」くらいにしか思っていない。そのうえ店でバイトをしている割にはろくに挨拶もしない。小柄でおかっぱ頭、ほっぺたは赤く田舎から出てきたばかりの「今時のわけのわからん少女か。」としか思っていない。「わたし、ジャズ研で歌っているんですよ」。
その日は客も少なく、トリオもいまいちで加藤の気分は滅入りがちであった。
スタンダードを歌わせて伴奏をするなんて全くやる気がなかったので一発ものでスキャットをさせてみた。
あのショックは忘れられない。スキャットはいつまでも止まらず、そしてそれは今まで聴いたことのないものだった。我々の世代では恥ずかしくてできないようなことを何の衒いもなく全身全霊で歌うのだ。それは美しいとか崇高とかいうものではなかったが、とにかく面白かった。
上質の音楽は笑いたくなる瞬間がある。それはほんとうに楽しいからであって可笑しいからではない。冗談音楽はきっちりとした計算の上に成り立つが即興演奏はそうではない。
瞬間のパッションである。計画しようがない空間、時間軸で瞬間的に放つエネルギーである。
つくられたもの、用意されたものでないから瞬間的な強烈なエネルギーで心を打つのである。ソプラノの音域で、しかもあどけない声質でブルースからファンクなどをシャウトするのである。リズム感、音程が素晴らしい。母はチャーリー・パーカーの肖像画を部屋に飾るくらいのジャズファンで父親はドラマーだったそうだ。幼いころからピアノとバイオリンをやり、チック・コリアのスペインを子供のころから口ずさんでいたそうだ。サラ・ヴォーンなど父親の趣味でしょっちゅう聴かされていたようだ。また本人はブラジル音楽に非常に興味を持っていて、当時日本にいたLuizao Maiaというエリス・レジーナ(ブラジルの国民的歌手)のバンドに在籍していたべーシストに認められ、彼のバンドでも歌っていた。
しかしその時は私のトリオでは使い物にはならなかった。あまりにも本能的で原始的だったのである。いやあるいは使いきれないという危惧があったのか。(その片鱗はコンペイトにある)
加藤はあの声、一般にジャズボーカルは低い声がうけるがあの声、正反対のソプラノである。頭にこびりついてしまった。あのスキャットをどうにかできないか。もともとビートルズが出発地点である加藤は自分のバンドにヴォーカルがあるのは何も不思議なことではない。しかしジャズに関してヴォーカルは別物である。ジャズは個々の音楽性を尊重する。いわば民主主義的音楽である。それを承知で集まって「JAZZる」のである。
個人を押えこむのはルール違反。無理である。特にヴォーカルに関してはいくらスキャットとはいえ完全にインストルメント扱いにはできない。しかし加藤は最終的にNOBIEを迎えることとなる。あのスキャットの魅力には勝てなかったのだ。
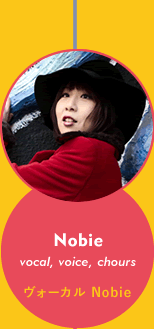


そして2003年、ローヴィング・スピリッツを通じてデビューアルバム「Endless Journey」を制作する。アルバムは当然、まるで共通項のない音楽の集まりになった。加藤のオリジナルが中心で半分はトリオ演奏だったが、NOBIEの歌った「Four」「Seven Steps To Heaven」などのカヴァーが話題を呼んだ。
そして翌年、セカンドアルバム「Se ャットやシャウトが新しい何かを感じさせたのかもしれない。
NOBIEはろくなリハーサルもしないのに新しい曲を次々とものにしていった。客が少なくてもまるでスタジアムで演奏しているように歌った。加藤はそのたびこの小柄な女のパワーに驚いた。
「まさにリトル・ダイナマイトだ」。
その後演奏活動は続けていたが若干のマンネリ化も感じていた。曲は演奏するたびこなれていき、グループサウンドというものを確実にものにして、なお且つ個人個人の演奏技術も進歩していった。だが予定調和は起きる。お互い手の内は読めるのでそこからの脱出は難しい。客を前にしてのパフォーマンスの失敗はプロとして許されないことも若い連中も感じ始めていた。加藤は解散を考えた。「もしメンバーの一人でも欠けることがあれば解散しよう。」
加藤はこの時期メンバーが辞めたいと切り出すのを密かに期待していた。
だが誰もそれを言わない。むしろ「楽しい」というのだ。リーダーとしてはこれほどうれしいことは無いが同時につらいことでもあった。

加藤はマンネリ打破、バンドのための新たな触媒として他の楽器を使うことを検討し始めた。サックス、トロンボーン、パーカッション、ギター、バスクラリネットいずれも決定項とはならない。またリスナーからはライブアルバムのリクエストもあった。すでに「Kamui Mosir」「Fabulous」等何曲かはリ・アレンジしてある。加藤は木管アンサンブルを取り入れることを考えていた。レコード会社は予算組の段階でアルバム化を保留していた。何しろ売れていない。
2008年から加藤はB-HOT CREATIONSと同時にスガ・ダイローとのジャズサムライ(3作ある)浅川太平との「Melody by Contrabass」という室内楽シリーズも進めていた。バンドは開店休業状態である。
そんな矢先、またライブレコーディングの話が浮上した。
木管アンサンブルを使って雄大な景色を夢見ていたが、どうにも大編成は経済的理由により不可能らしい。(なんでも思いどおりになる世の中よりはむしろこのほうが健全か。)
加藤は木管のなかでもフルートに注目した。加藤のイメージする大好きなモデルとなるバンドに初期のリターン・トウ・フォーエバーがある。ブラジルのヴォーカル、フローラ・プリム。そしてテナー・サックスのジョー・ファレルはフルートもやる。
以前演奏したことがある太田朱美を思い出した。そして彼女はジョー・ファレル・ファンであることを聞いていた。
「こいつなら面白いかもしれない。」
加藤はNOBIEと太田朱美がフロントに並ぶ絵を思い描いた。何気なくドラマーの橋本学(太田朱美バンド)から情報を集める。そして誘った。
太田はグループに参加するに何の躊躇も見せなかった。というかポーカーフェイスなのである。いったい何を考えているのか。
しかし参加後、想像以上の働きをみせた。アドリブはどの演奏も完璧で、アンサンブルにおけるオブリガートがまた絶品だった。そして右隣にいるじゃじゃ馬娘との相性もいいようだ。
まるで意図していなかったが偶然二人は同じ歳であった。そして太田は広島大学。ともに高学歴である。
新しい高学歴女性同年代2トップ体制が始まる。バンドはがぜん活気だった。懸案のライブアルバムを視野に入れライブ活動を続ける。
ローヴィング・スピリッツの社長、冨谷の意見も入れ信正と太田にそれぞれオリジナルを書いてもらうことにした。



そして2011年10月30日新宿ピットインでのライブレコーディングを迎える。
前回のライブは8月31日で2カ月空いた。そのうえで突然のライブレコーディングは危険かと危惧したがあえて決行。レコーディングはこの日一日のみ。ピットインは昼の部もあるので十分なリハーサルはとれない。が、やりきる自信はあった。
緊張度は高まる。つづく・・・・
結果は今、あなたが耳にしているとおりです。いかがでしょう?
追記:トラックダウンは加藤が中心に独断的に行ったので曲間の加藤のくだらないトークはカットしました。曲順は若干変更しました。
First set
1, Fly with the Wind (McCoy Tyner)
2, Fabulous (Nobie / Shinichi Kato)
3, Well You Needn’t (It’s Over Now) (Mike Ferro / Thelonious Monk)
4, Sunflower (Akemi Ohta)
5, Bass Folk Song (Nobie / Shinichi Kato)
6, Confeito (Shinichi Kato)
7, Set Me Free (Nobie / Shinichi Kato)
Second set
8, Take the “A” Train (Billy Strayhorn)
9, Sasayaki (Nobie / Shinichi Kato)
10, Biko (Shnichi Kato)
11, Tombo in 7/4 (Airto Moreira)
12, Variations on a Theme by Kamuy Mosir (Nobumasa Tanaka)
13, Kamuy Mosir (Obri Villon / Shinichi Kato)
14, Endless Journey (Nobie / Shinichi Kato)
15, Better Git it in your Soul (encore) (Charles Mingus)
前回のライブは8月31日で2カ月空いた。そのうえで突然のライブレコーディングは危険かと危惧したがあえて決行。レコーディングはこの日一日のみ。ピットインは昼の部もあるので十分なリハーサルはとれない。が、やりきる自信はあった。
緊張度は高まる。つづく・・・・
結果は今、あなたが耳にしているとおりです。いかがでしょう?
追記:トラックダウンは加藤が中心に独断的に行ったので曲間の加藤のくだらないトークはカットしました。曲順は若干変更しました。
First set
1, Fly with the Wind (McCoy Tyner)
2, Fabulous (Nobie / Shinichi Kato)
3, Well You Needn’t (It’s Over Now) (Mike Ferro / Thelonious Monk)
4, Sunflower (Akemi Ohta)
5, Bass Folk Song (Nobie / Shinichi Kato)
6, Confeito (Shinichi Kato)
7, Set Me Free (Nobie / Shinichi Kato)
Second set
8, Take the “A” Train (Billy Strayhorn)
9, Sasayaki (Nobie / Shinichi Kato)
10, Biko (Shnichi Kato)
11, Tombo in 7/4 (Airto Moreira)
12, Variations on a Theme by Kamuy Mosir (Nobumasa Tanaka)
13, Kamuy Mosir (Obri Villon / Shinichi Kato)
14, Endless Journey (Nobie / Shinichi Kato)
15, Better Git it in your Soul (encore) (Charles Mingus)
© Roving spirits ALL Rights Reserved.



